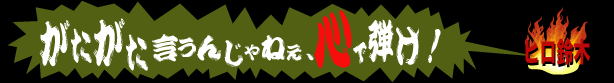« 第25回:自分に毒を盛れ! | メイン | 第27回:緊張感(その二) »
2006年01月30日
第26回:緊張感(その一)
ある新聞のスポーツ欄に、プロ・サッカーの中田英選手と全日本チームのジーコ監督の記事が出ていた。中田選手は「全日本チームの中でプレーする時、『和』を乱したくないから、チームメイトに意見するのはもうやめたほうが良いのかもしれない。」とジーコ監督
に相談し、監督はそれを受けて「思った事を率直に指摘することが世界のサッカーでは当り前のこと。欧州でプレーしてきた彼の心配が良くわかる。」と答えたそうだ。組織を重視するあまり、高い創造性を持った選手達が「個」の力を発揮できずにいるなら、システムがここまで系列化された世界のサッカーを日本が勝ち抜くことはないだろう、とも指摘していた。これはけして早朝草野球の話ではない。悲しいことにこれは日本プロ・サッカーの話、れっきとした「プロ」の世界での話題なのだ。
言わずもがな、一度名前にプロとつけば、それはジャンルに関わらず競争社会を意味するだろうし、ましてやそれが勝った負けたのスポーツとくれば、その競争もより熾烈なのだろうとの想像に難くない。「自分が活躍してチームも勝つのが一番、自分が活躍してチームが負けるのが2番、自分が活躍しなくてもチームが勝つのは3番、自分も活躍せずチームも負けるのが最悪。」と、あるプロ野球の選手が言っていた。2番と3番の順序は意見の分かれるところだろうが、やはりこれはプロの本音だろう。ひとつの目的の元に複数の「個」が集まってこその「チーム」なのだから、時にはそれぞれの「個」が真っ向から意見をぶつけ合って当然だと思うし、そうすることで生まれるエネルギーは目的達成への大きなベクトルになるはずだ。もちろん、とりわけプロの世界では、あくまでも意見を発した者が最後まで責任を持つわけだから、それ相応の覚悟に基づいたうえであることは当然だ。「個」を強く主張し合う責任感も覚悟も持てないことへの言い訳に「組織重視」とか「『和』を以って尊し」などと口走るとしたら、それはただの甘えだと思うし、「個」を殺さなければ生まれない「和」など所詮は傷の舐め合いの場に過ぎず、世界に匹敵する厳しいフィールドは国内に根付くことなく、ダブル・スタンダード、「日本は日本、世界は世界。」といった言葉で表されるような緊張感のない気風がいつまでもこの国を支配し続けることになるのだろう。
例えば、レコードや教則本を購入し、長年にわたって大きな影響を受けてきた憧れミュージシャンと共演するチャンスに恵まれたとする。それは自分にとって大変な光栄だし、当然相手に対する憧れも今まで以上に膨らむはずだ。でも空間と時間を共有し、ステージに上がる以上は、一対一の人間同士として視線の高さや体温の高さに違いがあってはならないはずだ。「胸を貸す」だとか借りるだとか、優越意識や遠慮、「先輩、後輩」などというなまぬるい気持ちはステージの上には絶対に持ち込み禁止だ。ライヴ音楽の緊張感が台無しになる。真剣に自己を表現し遠慮なくぶつかり合い、そこにどんな「音楽」が生まれるのか、そして生まれてきた音楽のどの辺に自分が位置していたかを、冷静に見守り、次のステップへの足場にすればいいと思う。
このコラムでも今までに何回も触れ、日本の音楽仲間達との間でも頻繁ににのぼる話題の一つに「ジャムセッション」がある。帰国のたびに時間を見つけては出来るだけいろいろなジャムに足を運び、日本のミュージシャンがどんなことを感じながらどんなプレーをしているのかを少しでも体感しようとしてきたつもりだ。そもそもジャムセッションというのは、限られた時間の中で未知数のミュージシャン達を臨機応変にまとめながら進めてゆくという、もともと無理の多い「企画」なわけで、そこに集まるプレーヤー達全てを満足させることはとうてい無理だ。時にはとてもセッション参加など望めそうもないようなプレーヤーがやってきたり、またその正反対に、信じられないような名プレーヤーがふらりと立ち寄り、順番をすっ飛ばしてでも参加してもらったり、つまりそこに集まった全てのオーディエンス、プレーヤーを飽きさせず、また不満を持たせずに高いクオリティーを保ちながらジャム・セッションを継続させるのはとても大変な作業なのである。そのためにどうしても欠かせないことは、そこに集まった全てのプレーヤーがエゴを捨て、音楽を楽しみ、共有し、お互いの音を注意深く聴き、リスペクトしようと努力することだと思う。もちろん、それを誰よりも率先しなければならないハウス・バンドの役目はとても重要だ。
今回、3月1日(水曜日)のウェルカムバック(東京)で、日本国内では初めてハウスバンドのメンバーとしてジャムに参加することになった。これは「北川純『ブルース青年会議所』ジャムセッション」という、謎のタイトルがついたジャムで、どれくらいの規模なのかはまだわからないが、俺もここニューヨークから出来るだけ多くのプレーヤーに声をかけて、参加する全ての人が「また来年も。」そして「来年こそは!」と思える刺激の多いジャムにしたいと思う。今からとても楽しみだ。
「憧れのミュージシャン」と一言でいうけど、考えてみると何人もの名前が浮かんでくる。もう何度も一緒にプレーしてきたG.J.JUKEのドラマー、ヨシさんも間違いなく憧れの
アーティストの一人だし、先週末にセッションしたエルヴィン・ビショップ
(http://blog.livedoor.jp/bloghirosuzuki/)や、昨年ミシシッピでビールをおごってくれたディッキー・ベッツも、同じステージに上がれば俺の膝は今でもガクガクと震え出す、大きな大きなインフルーエンスだ。
このコラムの#12でも触れたが、プロのミュージシャンを志して3〜4年目の頃、自分のスタイルをこのまま通して良いのかどうか随分と迷っていた時期があった。そんな迷いをいっきに吹き飛ばし、「これでいいんだ!」と強い自信を持たせてくれた二人の「憧れのミュージシャン」の演奏する二つの映像がある。一つはアメリカの有名なコメディー番組「サタデー・ナイト・ライヴ」の特別編集版「ベスト・オブ・ジョン・ベルーシー」で、このビデオの中に度々出てくるブルース・ブラザーズのギタリストの一人、スティーヴ・クロッパーが、新品のテレ・キャスターをフェンダー・スーパー・リヴァーヴに直で突っ込み、エフェクトも飾り気もない超アナログなリア・ピックアップ・トーンとレッド・ゾーンを軽く振り切るようなヴォリュームでもって、リズムギターをギャリギャリと弾きまくり、ヴォーカルを邪魔どころか完璧にサポートしているのを観て、なんだか寝ぼけていた頭が突然クリアになり、エレクトリック・ギターの持つ可能性のデカさを思い知らされたような気がした。
そしてもう一つの映像は、確かテレビの深夜放送の録画で、ジャズ・シンガーの金子晴美のライヴ映像。そのバック・バンドで、確かセイモア・ダンカン製のサンバースト・ストラト・キャスターを、やはりアンプに直でつなぎ、少ない音数と抜群の「間」で「歌わせて」いた塩次伸二のプレイに釘付けになり、何度も何度も繰り返し見て、そしてカセットテープにダビングして何度も聴いた。こんな説得力のあるギタリストが日本にいた事がとても嬉しかったし、この映像の中での彼のトーンは、自分自身がギターを語る時には今でも必ず思い出す、ひとつの「原点」の役割をしている。また、もう一つ、この塩次伸二のプレーで忘れられないのが、確かこれも同じ頃だったと思うのだが、ロバート・クレイが初来日した時、ある深夜テレビ(司会が村上里佳子だった?)がブルースを取り上げ、日本を代表するブルース・アーティストとして近藤房之助(G&Vo)、松本照夫(Dr)、塩次伸二(G)、妹尾隆一郎(Harp&Vo)(ベーシストが思い出せない。確か、当時ブレイク・ダウンでプレーされていた方だったような...)が紹介され、このユニットで2曲を演奏した映像だ。一曲目は妹尾隆一郎の歌う “Everything’s Gonna Be Alright”、そしてもう一曲が近藤房之助の“Sweet Little Angel”。とても短いセッションだったが、とにかく塩次伸二のプレーの強烈な説得力には圧倒され、特に二曲目のスロー・ブルースでのギター・ソロなどはギターが鳴りまくり、どこを切ってもオリジナリティーの溢れ出る、最高最強のソロだった。一昨年の秋には塩次伸二氏率いる「S・S・B」のショーにゲスト出演させていただくという大変なラックに恵まれ、その後も塩次氏にはいろいろとお世話になっている。そして今年の2月23日には大阪新世界COCOROOMでのショーへ再び参加させていただけることが決まった。ガクガクいうに決まっている膝を大阪ディープ・サウスの地面にぐぅーっ踏ん張り、通天閣の展望台から飛び降りる覚悟で、緊張感と充実感のある図太い演奏をしたい。そして日にちは前後するが、その前日22日には「塩次伸二・ギター・トレーニング・ジム・京都校」にゲスト参加させていただくことになった。「ゲスト参加」というよりも、ここではむしろ俺は参加する生徒さんたちの視線から、「塩次伸二」という偉大なアーティストの「音楽」を超積極的に盗んでみたいと思うし、そして同時に日本の若いミュージシャンが「塩次伸二」をどんな風に感じながらプレーしているのかをじっくりと見つめさせていただきたいと思っている。
このニューヨークから遠く離れた日本の関係者達とコミュニケーションを密に取り合うことは思いのほか難しい。14時間という時差に加え、お互いがミュージシャンという仕事柄、自宅にいない場合が多いため、どうしても携帯電メールに頼らざるを得なくなる。4人のバンドメンバー、対バンやゲスト出演のミュージシャン達、ライヴハウスやラジオ局の方達、XoticやDr.Z等々を全面的にサポートしてくれるPCIの方達..と、ここまで多くの日本サイドの関係者と必要最低限に短くまとめた文章を繰り返しやり取りするうちに、個々の会話の脈絡が内容的にも時間的にも交錯し、気をつけていないと一体誰と何の話をしているのかがわからなくなり、自分の事務能力の低にうんざりしてしまうことになってしまうわけだ。どうやら、いちどの送信に複数の用件は禁物、一回につき一つの用件にとどめること、そして返事を気長に待つゆとり、強いていうなら、この二つがコツみたいだ。どんなにデジタル化されても、それを操るのはただの人間だ。あせらずやろう。
最近、THE BANDの解散コンサート、「THE LAST WALTZ」のDVDを手に入れた。解散を決め、最後のパフォーマンスを大きなコンサートで締めくくるメンバー一人一人の微妙な「温度差」が言葉と言葉の間からうかがえるような気がして興味深い。しかしステージの上では、全員が「THE BAND」という目的の元に一つになり、お互いを尊敬し信頼しつくしながら音楽を創りあげてゆくさまを見ることができる。ひたむきに淡々と、まるでキャンバスに大きな絵を描いているようだ。このライヴの中では“THE NIGHT THEY DROVE OLD DIXIE DOWN”がいい。それに “UP ON CRIPPLE CREEK”も。このシンプルさと力強さは、20年近くを同じメンバーで続けてきたユニットならではだろうか。つくづくこんなバンドをやりたいと思う。 今回の俺の日本ツアーでは、アメリカン、特にサザンロックのスタンダードをカバーする機会がありそうなので、今その準備をしているところだ。(つづく)
日本ツアーの詳細はこちら


1月20日にニューヨークのB.B.キング・クラブでエルヴィン・ビショップのショーがあった。エルヴィンの音楽には、いつも俺の心を暖かく包んでくれる何かがある。
P.S.
毎度のことながら、投稿が遅れてホントウに申し訳ない。最近は物理的に時間が足りないし、それに構想に思いをめぐらせる精神的時間の余裕も少ない。やらなければならないことが目白押しで、こうして徹夜でバシャバシャとやっている。「がんばれ!」というメールを多くの読者の方からいただく。それらがどれだけ励みになっていることか。
ありがとう、頑張ってやっています。もうすぐ春だ!
ヒロ鈴木のWebsiteはこちら
ヒロ鈴木のVideo映像はこちら
ヒロ鈴木のインタビューはこちら
ライブレポートはこちら
投稿者 admin : 2006年01月30日 10:15